軒を貸して母屋を取られる

何やら領土をめぐる争いが激しくなってきましたので、所謂領海に関する知識をまとめてみます。
自国の領海に関しては、領土の基線からの距離に基づいて、3つの国際法的解釈があるようです。
当然ですが、遠くなるに従って、主権が及ばなくなっていきます。
領土の基線から12海里(約22km)までの水域。領土と同じく主権が及ぶ範囲ではあるが、外国船の通航は認められている。ただし、沿岸国の無害通航関連の法律順守を求められる。
領海の基線から12海里(約22km)までの水域(つまり領土の基線から24海里)。領海の外縁にあり、接続水域で国家は自国内または領海内における通関、財政、出入国管理、衛生に関する法令の違反について防止や処罰を目的とした措置をとることができる。接続水域は本質的には公海であり、規制対象船舶は領海に侵入していない以上違反行為の実行の着手はまだ無いと見るべきであることから、事実上の予防に留まり、強制措置まで含まれないと解されている。領海とは異なり、接続水域を巡る紛争の解決のための規定はなく、当事国は妥協点を模索して協議しなければならない。
領土の基線から200海里(約370km)までの水域(つまり接続水域の基線から176海里)。経済的な主権がおよぶ水域のことを指す。沿岸国は国連海洋法条約に基づいた国内法を制定することで水産資源および鉱物資源などの非生物資源の探査と開発に関する権利を得られる。その代わりに、資源の管理や海洋汚染防止の義務を負う。一方で、無害であろうと戦闘目的であろうと、領海外の排他的経済水域では水面上や水面下での通過や航行に対して規制や禁止することはできない。

これで【中国船が接続水域航行】なんてニュースが流れても、大体どこら辺を航行しているのか分かりますね。
スポンサーリンク
スポンサーリンク



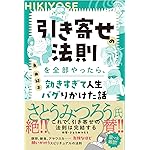
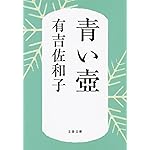

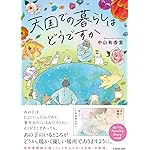
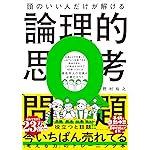
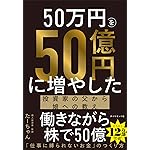
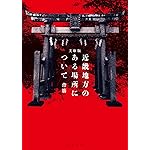
最近のコメント