 突然ですが、あなたはパソコンを選ぶ時、何を一番重要視しますか? 性能? 価格? デザイン? それとも、直感ですか?
突然ですが、あなたはパソコンを選ぶ時、何を一番重要視しますか? 性能? 価格? デザイン? それとも、直感ですか?
私はこれまで、数えきれないほどのパソコンを渡り歩いてきました。
用途も様々で、文章作成、動画編集、プログラミング、そして最近では3DCG制作にも挑戦しています。
そんな私が今回、最新のM4 MacBook ProとMacBook Air、そして長年愛用しているWindowsデスクトップとノートPCの計4台を徹底的に比較検証してみました。
「M4 Macは本当にWindowsを打ち負かせるのか?」
「クリエイターにとって、どちらのOSがより快適なのか?」
この記事では、そんな疑問を解消すべく、CG制作の現場で実際に使用されるソフトウェアを使い、様々な角度から検証した結果を、余すことなくお伝えします。
パソコンの買い替えを検討している方はもちろん、これからCG制作を始めようと思っている方にも、きっと役立つ情報が満載です。
ぜひ最後までお付き合いください。
M4 MacBook Pro vs Windows:CG制作最強マシンはどっちだ?
今回比較検証に使用するパソコンは、以下の4台です。
- M4 MacBook Pro (M4 Max)
- M4 MacBook Air
- Windows デスクトップ (自作)
- Windows ノートPC (2021年モデル)
1. M4 MacBook Pro (M4 Max):最強スペックの実力は?
まずは、Apple Storeで現時点で最もハイスペックなM4 Max搭載のMacBook Proからご紹介しましょう。
正直、めちゃくちゃ快適です。
個人的には、Windowsのデスクトップよりも性能が良いことを期待しています。
2. M4 MacBook Air:ライトユーザーには十分?
続いて、M4チップを搭載したMacBook Airです。
比較しやすいように、Apple Storeで販売されている真ん中の価格帯のモデルを選びました。
メモリも最低ラインの16GBなので、Blenderが推奨する最低構成を何とか満たしているというスペックです。
Unreal Engineの推奨最低構成も満たしていますが、高性能とは言えません。
このM4 MacBook Airが、どこまでサクサク動いてくれるのか楽しみです。
3. Windows デスクトップ (自作):快適なCG制作環境
3台目は、半年前くらいに自作したWindowsデスクトップです。
BlenderやUnreal Engineなどが快適に動かせるように、各パーツを吟味して組み立てました。
グラフィックカードは一世代前のものになりますが、それでも十分に快適に作業できています。
価格は約35万円で、中の上のスペックといったところでしょうか。
4. Windows ノートPC (2021年モデル):旧世代PCはどこまで通用する?
最後に紹介するのは、2021年にサブ機として購入したWindowsノートPCです。
当時はノートPCとしては充実したスペックでしたが、4年前のモデルなので、最新のパソコンと比べてどのくらいの性能差があるのか気になるところです。
価格は当時20万円くらいだったと思います。
Blender vs Unreal Engine:M4 Macの真価が問われる
今回の検証では、BlenderとUnreal Engineという、CG制作の現場でよく使われる2つのソフトウェアを使用します。
それぞれのソフトウェアで、以下の項目を比較検証していきます。
Blender
- リアルタイムの描画性能
- 操作性
- 物理演算の速度
- レンダリングの速度
Unreal Engine
個人的には、Unreal EngineはWindowsで動かすイメージが強いので、M4 Macでどのくらい動いてくれるのか期待したいですね。
Blender検証:リアルタイム描画、物理演算、レンダリング速度を比較
それでは、いよいよ比較検証に入っていきましょう。
まずはBlenderから検証していきます。
リアルタイム描画性能:M4 Macはスムーズ?
まずは、リアルタイムの描画性能を検証します。
水面にオブジェクトが浮いているシンプルなシーンをタイムライン上で再生し、どのくらいスムーズに動くのかを比較します。
M4 Max MacBook Pro
再生してみると、かなりスムーズに動いています。
カクつきもなく、特に変な挙動も見られません。
ただ、オブジェクトに少し残像が見えるのが気になります。
M4 MacBook Air
同じシーンを再生してみると、M4 Max MacBook Proとほとんど変わりません。
本当にごくわずかに、カクつくようなタイミングがあるような気もしますが、ほぼスムーズに再生できています。
残像についても、MacBook Proと同じように見られます。
Windows デスクトップ
Windowsデスクトップでも、問題なく再生できているように見えます。
ただ、よく見るとM4 Macよりも少しだけカクつきがあるように感じます。
普段の作業レベルでは気にならない程度だと思います。
Windows ノートPC
WindowsノートPCでは、他の3台に比べて明らかにカクつきがあります。
4年前のパソコンなので仕方ないですが、それでも頑張ってくれている方だと思います。
4台を並べて比較してみると、ほとんど差がないように見えますが、Macの方がスムーズに動いているように感じます。
これは、CPUの性能がMacの方が優れているからかもしれません。
EEVEEレンダリング:操作性とレンダリング速度
続いて、EEVEEレンダリングエンジン用に作られたシーンを使って、操作性とレンダリング速度を検証します。
実際にカメラやオブジェクトを動かして、どのくらいスムーズに作業できるのかを比較します。
M4 Max MacBook Pro
シーンを動かしてみると、かなりスムーズです。
全くストレスを感じません。
ネズミのキャラクターの顎のあたりに少しノイズが見えますが、これは仕様でしょうか。
このシーンをレンダリングしてみたところ、9秒で完了しました。
4Kの解像度で、比較的複雑なシーンにもかかわらず、かなり早くレンダリングできたと思います。
M4 MacBook Air
MacBook Airでも、案外スムーズに操作できています。
ただ、MacBook Proに比べると、少しもっさり感があるように感じます。
ネズミの顎には、やはりノイズが乗っています。
ソファーを動かしてみると、結構カクカクします。
M4 Max MacBook Proと比べると、スペック的に見劣りしてしまう部分です。
このシーンのレンダリングには、35秒かかりました。
M4 Max MacBook Proと比べると、3倍以上の時間がかかったことになります。
これは、スペック的に仕方ないでしょう。
Windows デスクトップ
シーンを動かしてみると、かなりスムーズです。
さすがRTXシリーズのグラフィックボードといった感じですね。
ネズミの顎のノイズは、こちらにも見られます。
ソファーを動かしてみると、ぬるぬる動いてくれます。
全く問題ありません。
レンダリングにかかった時間は、6秒でした。
今までで最速です。
Macに勝ちました!
やはり、GPUの性能が求められるシーンでは、Windowsが強いですね。
Windows ノートPC
シーンを動かしてみると、少しだけカクカクします。
グラフィック性能の差が顕著に出ている感じです。
ネズミの顎には、なぜかノイズがありません。
これは不思議ですね。
ソファーを動かしてみると、結構スムーズに動いていますが、WindowsデスクトップやM4 Max MacBook Proに比べると、若干カクカクしているように感じます。
レンダリングにかかった時間は、14秒でした。
M4 MacBook Airよりも全然早く、半分くらいのスピードで終わりました。
4年前のパソコンとは思えないですね。
このシーンに関しては、Windowsの圧勝と言えるでしょう。
物理演算:流体シミュレーションの速度
続いて、物理演算の速度を検証します。
流体が注がれるシンプルなシーンで、物理演算をどれだけサクサク計算してくれるのかを比較します。
M4 Max MacBook Pro
シーンを開いた状態で、レンダービューに切り替えます。
物理演算のプロパティで、キャッシュのタイプを「全て」から「リプレイ」に変えると、正常に表示されました。
再生ボタンを押すと、物理演算が始まりました。
かなり早く計算してくれているように感じます。
液体が注がれるほど形状も複雑になり、計算が重くなっていくはずですが、なかなか早く計算してくれています。
結果は、2分1秒でした。
体感としては、結構早かったです。
M4 MacBook Air
計算を開始すると、もっと遅いかと思っていましたが、意外とサクサク計算してくれています。
これは意外です。
結果は、2分54秒でした。
MacBook Proよりは遅いですが、かなり早く計算してくれたのではないでしょうか。
すごいですね。
MacBook AirのM4チップのCPU性能は、かなり優れていると言えるでしょう。
Windows デスクトップ
計算を開始しましたが、少し時間がかかりそうな感じです。
M4 Macを見た後だからかもしれませんが、少し遅く感じます。
結果は、3分29秒でした。
これは少し時間がかかりましたね。
M4 Max MacBook Proの約1.5倍くらいの時間がかかりました。
CPUの性能が顕著に出るのでしょうか。
Windowsデスクトップも良いCPUを積んでいるのですが、Macはすごいですね。
Windows ノートPC
かなり厳しい戦いになると思いますが、頑張ってほしいですね。
シミュレーションを開始しましたが、見るからに遅いです。
これは仕方ないでしょう。
結果は、8分52秒でした。
これは遅いですね。
4年前のノートPCなので、仕方ないでしょう。
物理演算は、Macに軍配が上がる結果となりました。
Cyclesレンダリング:教室シーンのレンダリング速度
最後に、Cyclesレンダーエンジン用に作られたシーンを使って、レンダリング速度を検証します。
教室に光が差し込む複雑なシーンで、1枚の画像を書き出すのにどのくらい時間がかかるのかを比較します。
M4 Max MacBook Pro
レンダープロパティのデバイスがCPUになっているので、GPU演算に変更します。
プレビューが描画されましたが、かなりスムーズに描画されています。
シーンのビューを動かしてみても、結構スムーズに動きます。
レンダリングを開始したところ、15秒で完了しました。
Cyclesで複雑なシーンにもかかわらず、かなり早く終わったのではないでしょうか。
M4 MacBook Air
デバイスをGPU演算に変更して、シーンを動かしてみましたが、プレビューが落ち着くまでにかなり時間がかかっています。
これは、サクサクとは言えないでしょう。
プレビュー表示に時間がかかっている感じがします。
レンダリングを開始したところ、1分20秒かかりました。
かなり時間がかかりましたね。
M4 MacBook Airは、GPUを使ったCyclesレンダリングが苦手なようです。
Windows デスクトップ
デバイスをGPU演算に変えると、プレビューがめちゃくちゃ早いです。
カメラを動かしてみても、これは早いですね。
Cyclesを使うと、GPUの性能が顕著に出ますね。
RTXシリーズのグラフィックカードは、やはり強いです。
レンダリングにかかった時間は、12秒でした。
めちゃくちゃ早いですね。
M4 Max MacBook Proとほぼ同じくらいの性能ですが、若干Windowsデスクトップの方が早いという結果でした。
Windows ノートPC
デバイスをGPUに変えると、描画されました。
思ったより早いですね。
カメラを動かしてみると、意外とサクサク動きます。
M4 MacBook Airと比べると、全然早いです。
スペック的にはM4 MacBook Airの方が上なのですが、CyclesでGPUを使うと、Windowsの方が全然強いですね。
レンダリングにかかった時間は、28秒でした。
結構早いのではないでしょうか。
M4 MacBook Airの1/3くらいの時間で終わってしまいました。
これは意外ですね。
このシーンに関しては、Windowsの圧勝と言えるでしょう。
Unreal Engine検証:操作性とレンダリング速度
ここまではBlenderを使って検証してきましたが、次はUnreal Engineを使って検証していきます。
Unreal Engineは、元々ゲームを作るために開発されたソフトウェアなので、主にGPUを使ったリアルタイムの描画性能が求められると思います。
M4 Max MacBook Pro
今回は、Unreal Engineのマーケットプレイスで無料で配布されている「Automotive Configurator」というファイルを使っていきます。
立ち上げに少し時間がかかっていますが、立ち上がってから画像が落ち着くまでも、まあまあな感じです。
そんなに遅い感じはしません。
あらかじめ用意されているタイムラインを使っていこうと思うので、「Content」 > 「CarConfigurator」 > 「Comercial」 > 「Sequence」の中にある「Cine_SizzleMaster」というレベルシーケンスを使っていきます。
レベルシーケンスが開かれました。
カメラのボタンを押して再生ボタンを押してみます。
これはまだレンダリングをしているわけではなくて、ただプレビューを見ているだけなのですが、かなりスムーズに動いてくれています。
リアルタイムでここまで再生できるのは、処理としては早いのではないでしょうか。
全部で670フレームくらいの映像ですが、これを1080HDのJPEGで書き出すとどのくらい時間がかかるのか検証してみようと思います。
シーケンサーのカチンコマークのアイコンをクリックして、ムービーレンダーキューを出します。
設定も最初からされているので、このまま書き出そうと思います。
レンダリングのローカルとリモートは、どちらでも良いと思いますが、今回はレンダリングローカルで行こうと思います。
レンダリングを開始しましたが、シェーダーのコンパイルなどで少し時間がかかっています。
結構スムーズにレンダリングできているのではないでしょうか。
結果は、1分7秒でした。
個人的な体感ですが、結構早いのではないでしょうか。
VIPORTの作業画面上でのスムーズさも検証していきます。
車を中心にぐるぐるカメラアングルを回してみますが、M4 Max MacBook Proは結構スムーズに動いているのではないでしょうか。
ぬるぬる動いている感じがします。
M4 MacBook Air
先ほどと同じくタイムラインをリアルタイムで再生してみますが、大体問題ないように見えますが、少しだけカクつきとか少し処理の重さを感じますね。
普通に再生できているのは、すごいのではないでしょうか。
レンダリングを開始しましたが、なんだかシェーダーのコンパイルにすごい時間がかかっています。
処理性能の違いなのでしょうか。
レンダリングがちゃんと始まりましたが、さすがに少し時間がかかっている印象ですね。
結果は、6分7秒でした。
ちょっとかかってしまいましたね。
M4 Max MacBook Proの6倍くらいかかっています。
これは少し残念な結果となりました。
M4 MacBook Airも操作感を試してみたいと思います。
車を中心にぐるぐる回してみますが、少しカクついてるかなといった感じです。
作業する上では、そんなに気にならないかもしれませんが、M4 Max MacBook Proと比べると、ちょっとカクついている感じがします。
Windows デスクトップ
タイムラインをリアルタイムで再生してみます。
少しだけカクつきがあるようにも見えますが、かなりスムーズに再生できているのではないでしょうか。
全然問題ないですね。
レンダリングを開始したところ、なかなか早そうです。
結果は、29秒でした。
これは早いですね。
M4 Max MacBook Proの半分くらいの時間で終わりました。
やはり、やはり、Unreal EngineはWindowsで動かす方が適しているようですね。
GPUの処理が求められるシーンでは、専用のグラフィックボードを積んだWindowsの方が有利です。
総合評価:M4 Mac vs Windows、CG制作に最適なのはどっち?
様々な項目で4台のパソコンを比較検証してきました。
それぞれの特性が見えてきたところで、総合評価をしていきましょう。
1. M4 Max MacBook Pro
最も高価なマシンだけあって、全体的にバランスの取れた性能を発揮しました。
特に物理演算では圧倒的な速さを見せ、CPUの性能の高さを証明しています。
Unreal Engineの操作性も良好で、レンダリング速度も悪くありません。
ただし、GPUを使ったCyclesレンダリングでは、同等価格帯のWindowsデスクトップには若干劣る結果となりました。
総合評価:★★★★★(5/5)
用途を選ばず、どんな作業にも対応できる万能マシン。外出先での作業が多いクリエイターにとっては、この性能を持ち運べるのは大きなメリットです。
2. M4 MacBook Air
軽量なボディに搭載されたM4チップのCPU性能は、特に物理演算で光りました。
リアルタイム描画の性能も良好で、日常的な編集作業であれば十分な性能を発揮します。
ただし、GPUを使った処理、特にCyclesレンダリングやUnreal Engineのレンダリングでは苦戦する場面が見られました。
総合評価:★★★☆☆(3.5/5)
携帯性と基本性能のバランスが取れたマシン。モデリングやテクスチャ作成など、GPUへの依存度が低い作業が中心のクリエイターには十分な選択肢となります。
3. Windows デスクトップ
GPUを活かした処理では、全てのマシンの中で最も高いパフォーマンスを発揮しました。
特にCyclesレンダリングやUnreal Engineのレンダリングでは圧倒的な速さを見せています。
操作性も良好で、日常的な編集作業もストレスなく行えます。
唯一の弱点は、物理演算など一部のCPU依存の処理で、M4 Macに劣る結果となったことです。
総合評価:★★★★☆(4.5/5)
固定された作業環境で、GPUを活かしたレンダリングを多用するクリエイターにとっては最適なマシンです。コストパフォーマンスも考慮すると、デスクワークが中心のユーザーにはおすすめできます。
4. Windows ノートPC
4年前のマシンにもかかわらず、健闘しました。
特にGPUを使った処理では、最新のM4 MacBook Airを上回る場面もあり、Windowsマシンの強みを見せつけました。
ただし、全体的な性能は他の3台には及ばず、特に物理演算では大きく差をつけられる結果となりました。
総合評価:★★★☆☆(3/5)
4年前のマシンとしては十分な性能を発揮しており、軽めのCG制作であれば今でも現役で活躍できることを証明しました。
結論:目的に応じた最適なマシン選びを
今回の検証結果から、一概にどちらのOSが優れているとは言えないことが分かりました。
それぞれの用途や作業内容によって、最適なマシンは異なります。
CPUパワーが求められる物理演算や、MacOSに最適化されたソフトウェアを使用する場合は、M4 Macの選択が有利でしょう。
一方、GPUパワーが求められるレンダリングや、Unreal Engineなどのゲームエンジンを使用する場合は、専用グラフィックボードを搭載したWindowsマシンの方が適しています。
また、外出先での作業が多いクリエイターであれば、M4 Max MacBook Proのような高性能なノートPCが最適でしょう。
デスクワークが中心で、予算にも限りがある場合は、コストパフォーマンスに優れたWindowsデスクトップを選ぶのが賢明かもしれません。
私自身は、メインマシンとしてWindowsデスクトップを使いつつ、外出先ではM4 MacBook Airを使うという組み合わせが、現時点では最適だと感じています。
用途に応じて使い分けることで、それぞれのマシンの強みを活かしつつ、弱点を補完することができるからです。
最後に、パソコン選びで最も大切なのは、自分の作業スタイルや目的に合ったマシンを選ぶことです。
スペック表だけでは分からない、実際の使用感や操作性も重要な判断材料となります。
この記事が、皆さんのパソコン選びの一助となれば幸いです。
 突然ですが、あなたはパソコンを選ぶ時、何を一番重要視しますか? 性能? 価格? デザイン? それとも、直感ですか?
突然ですが、あなたはパソコンを選ぶ時、何を一番重要視しますか? 性能? 価格? デザイン? それとも、直感ですか?

 私はかつて、最新ガジェットに飛びつくタイプの人間でした。新しいiPhoneが出るたびに、予約開始日にオンラインストアに張り付き、発売日には行列に並んで手に入れるのがステータスだと思っていたのです。しかし、ある時ふと気づきました。「本当に必要なのか?」と。
私はかつて、最新ガジェットに飛びつくタイプの人間でした。新しいiPhoneが出るたびに、予約開始日にオンラインストアに張り付き、発売日には行列に並んで手に入れるのがステータスだと思っていたのです。しかし、ある時ふと気づきました。「本当に必要なのか?」と。


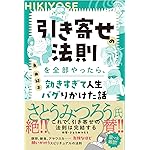
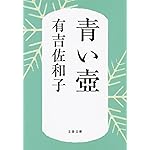

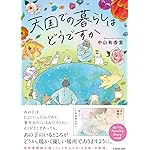
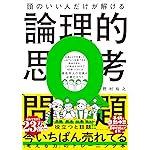
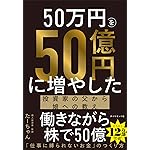
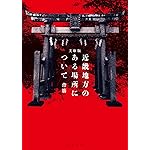
最近のコメント