仕事の流儀

プロジェクトとは何だろうか?
テキストにはこう書かれている。
特定の目標、目的を達成するために行われる一連の活動で、開始、中間、終了の段階を明確に特定できるもの
(クリティカルチェーン P.36)
それがプロジェクト。
つまり、恐らくほとんどの仕事がプロジェクトであり、仕事の経験があるなら大抵の人は何らかのプロジェクトを経験している。
仕事の進め方は様々だが、自分独りで完結する仕事は少ない。
多くの仕事が自分ではコントロールが難しい他者を介して行われることは少なくないだろう。
しかし、その仕事が自分の担当である場合には、その仕事をマネジメントする必要がある。
そんな時に役に立つのが、プロジェクトマネジメントの手法である。
プロジェクトも一つならいいが、多くが同時進行で、かつそれぞれ数多のタスクが伴う場合は有効な手法で管理しなければとても管理できるものではない。
プロジェクトに人員を追加することは、プロジェクトをかえって遅れさせがちだ。開発者間の可能な連携な数はグループの大きさに対して指数的に増大する。グループが大きくなればなるほど、スタッフは各ソフトウェアがどう協調すべきかを話し合うミーティングにより多くの時間をとられ、意図しなかった相互作用から生まれるバグも増えていく。
幸いなことに、このプロセスは逆方向にも動くんだ。グループが小さくなればなるほど、ソフトウェアの開発効率は指数的に増大する。Viawebで、プログラマがミーティングというものをしたことがあったか、思い出せない。昼食での会話以上に話し合わなければならないことを抱えていたことなんてなかった。
(ハッカーと画家 P.75)
確かに社内ですら、それぞれの人員・立場の意思統一に多くの時間と労力を割いている。
色々なことを調査し、分析し、報告書にまとめ、日本風に言えば根回しした上に、長い会議で合意を取り付けなければならない。
その結果問題が起きれば責任は「会議」ということになるのだが、結局は責任逃れのための時間稼ぎなのだ。
私は海外で働いていた時に「なぜ日本側は意思決定するのにこんなに時間がかかるのだろう?」といつも不思議に思っていた。
ビジネスや会社経営は民主主義では成り立たない。トップの判断で業績は良くも悪くもなる。多くの人が同意する意見が必ずしも正しいとは限らない。間違った上に判断が遅くなれば、過ぎ去った時間はどうやっても取り戻すことはできない。
それならば、必要なだけの人数で素早く意思決定すべきではないのか。
日本でも経営者の間で「新幹線経営」ということが一時盛んに言われていた。
今までは軍隊と同じで、先頭機関車の社長が後続車両の社員を引っ張って走っていた。しかしこれからは、社員全員がそれぞれ動力を持って走る新幹線にならなければならない、と。
先頭車両が後ろの車両を導き、しっかりとレールを走るならそれでもいいのかも知れない。
ところが社員全員がそれぞれの意思を持ち、走ったり走らなかったり、あるいは全然違う方向に走ろうとすれば、車両は脱線してしまうのではないか。
私がうまくいっていると感じた新幹線経営は、新幹線というよりも、むしろ独立した機関車だった。つまり、それぞれに役割・権限・責任を与え、それぞれに仕事を任せる。こういったやり方はうまくいっていた。
軍隊式マネジメントは全体を将軍の戦略に基づいて同じ方向に動かす。
新幹線経営ではレールに従いながらも、各自が動力としての役割を担う。
それぞれ良い面・悪い面がある。
もしプロジェクトを仕事の単位とするなら、小さな自動車のように走らせることはできないだろうか。
必要な人員だけ乗せた自動車が理想ではないか。
システム管理者は競争的なプレッシャーに晒されていないと、融通が利かなくなり、適切な反応ができなくなる。セールスマンは常に顧客に接しているし、開発者はライバルのソフトウェアと競わなくちゃならない。でもシステム管理者は、独身の老人のように、きちんとしなくちゃならないっていう外圧があまりないんだ。
(ハッカーと画家 P.80)
こういうことは社内で本当によくある。
プロジェクトを進めようとか、より良くしようというよりも、自分たちの立場を守ることの方が大事になってしまうことがある。
言い方が悪いが「面倒を嫌うだけの公務員」的な思考である。
デミングのメッセージは、経営者に向けて発せられたものだった。それは、経営者(経営幹部)はその役割を果てしてこなかったという、耳が痛くなるような辛辣なメッセージであった。このメッセージを目に見える形で説明しようと、デミングはセミナー参加者に製造現場を想定した実験を受けさせたのである。
セミナー参加者たちは、作業員、検査員、マネジャーの3つの役に割り振られた。作業員役には簡単な作業をさせた。目の前には白いビーズがドラム缶いっぱいに入っており、中にはわずかに赤いビーズが混じっていた。作業ではドラム缶を勢いよく何度も回して中身をよく混ぜ合わせるように教え、よく混ぜ合わせることが大切であると強調された。
次に50個の小さなくぼみのあるパドル(櫂)を渡された。くぼみはビーズ1個ずつが入るほどの大きさであった。ドラム缶のなかにパドルを通すと、作業員は正確に50個のビーズをすくい出せるようになっていた。参加者たちには、顧客クレームを防ぐために50個中赤いビーズが3個以上含まれてはならないと営業部門から決められており、またその目標に向かって努力しなければならないことが知らされた。作業員がビーズでいっぱいのパドルを持って現れると、検査員は赤いビーズの数をかぞえて記録した。マネジャーは記録を調べて、赤いビーズの数が少ないか、多くても許容量の3に近い作業員を誉め、赤いビーズの数が多い作業者を叱った。その証拠にマネジャーは、しばしば不器用な作業員の手を止めさせ、器用な作業員のやり方を観察するようにいい、課せられた仕事をどのように正確にこなせばいいか学ばせようとしていた。
ドラム缶のビーズのうち、5分の1は赤だった。赤いビーズが混じるのが3個以下となる確率は1%未満。しかし、赤いビーズが6個以下となる確率は約10%だったので、作業員は多くて3個の赤いビーズという届きそうで届かない魔法の目標に、しばしばじらされながら近づいていった。平均的には、作業員たちは10個の赤いビーズを取り出していたが、これは経営者が満足できるものではなかった。ことによっては13個から15個の赤いビーズを取り出す作業員もいたが、これは明らかに、かなり下手な作業の結果であった。
デミングが指摘したかったのは、経営者が一方的に達成不可能な水準を設定し、水準が達成可能かどうか、あるいは水準に合わせて技術を変えるためには何をすべきかなど考えようともしないことがあまりにも多すぎる、ということだった。それどころかアメリカの経営幹部は、水準の維持は品質管理の専門家に任せきりで、工場労働者が抱くであろう不満を無視している、とデミングは苦言を呈した。
アメリカの産業界に広まった経営方法の一時的な流行を、デミングは痛烈に批判した。1970年代に流行った謳い文句は「不良品ゼロ」であった。生産物に不良品がないという状態は、デミングにしてみれば完全にあり得ないのである。
1980年代には「総合的品質管理(TQC)」がもてはやされた。デミングはこれらすべてを中身のない言葉であり、現実の仕事をすべき経営者からの説教以上のものではない、と見ていた。
(統計学を拓いた異才たち P.313)
経営者ならずとも、無茶な要求をしてくる人は少なくない。それで体も心もボロボロになる担当者も多いだろう。
本来であれば、トップが上手に回る仕組みを作らなければならないのだが、聞こえのいい「新幹線経営」がまかり通り、経営者はその役割から逃げる。
貴社が抱える問題、すなわち低い生産高、高いコスト、品質のバラツキなどについて検討いたしました結果をご報告申し上げます。
トップ・マネジメントが責任を果たす姿勢がなければ、品質改善を成し遂げたとしても、恒久的な影響を持ちません。
品質の責任を負わず、責任に従って行動してこなかったあなたがたの経営こそが、私の考えでは、貴社の問題の主たる原因です。あなたがたの会社がしていることは、品質管理ではなく、ゲリラ的に狙いを撃つことです。システムは組織化されておらず、システムとして品質管理をすることの用意もなければ正しい理解もありません。あなたがたは、失火後、火が燃え広がる前に現場に急行できるよう願っている消防署を運営してきたようなものです。あなたがたがあちこちに貼っているスローガンは誰もがただ完璧に仕事をするように促すもの以外の何ものでもありません。どうやってそれを実践できるのか、私には疑問です。一人ひとりが自分の仕事を改善せよということでしょうか。自分の仕事が何なのか、またその改善方法を知る術のない人が、どうやって自分の仕事を改善することができるのでしょうか。原材料の欠陥、供給量の変更、機械の故障といった条件下ではいかんともしがたいでしょう。
別の障害は、製造に従事している労働者にすべての問題の責任があるとする経営者側の想定です。製造従事者が正しいと思っているやり方で仕事をしている限り、製造現場で問題が起きるはずがありません。
私の経験によれば、製造現場における多くの問題は共通の原因に根ざしていて、その原因は経営者側だけが減らしたり、除去したりできるのです。
(統計学を拓いた異才たち P.366)
管理者ばかりになっていないか。
国でも会社でも強いリーダーが求められているはずだ。




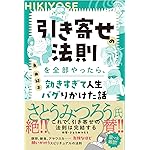
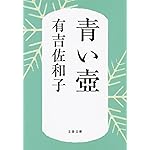

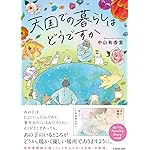
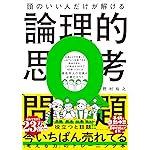
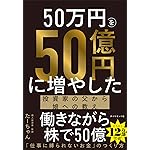
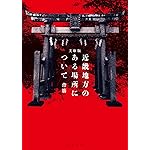
最近のコメント